退廃芸術
今日も生きてます。
キャンバスは下地が施された布が木枠に張られたものですが、表面はキャンバス地といってでこぼこしてます。
個人的にはこれが表現上扱いづらいと感じるため、やすりで磨きます。

磨く前
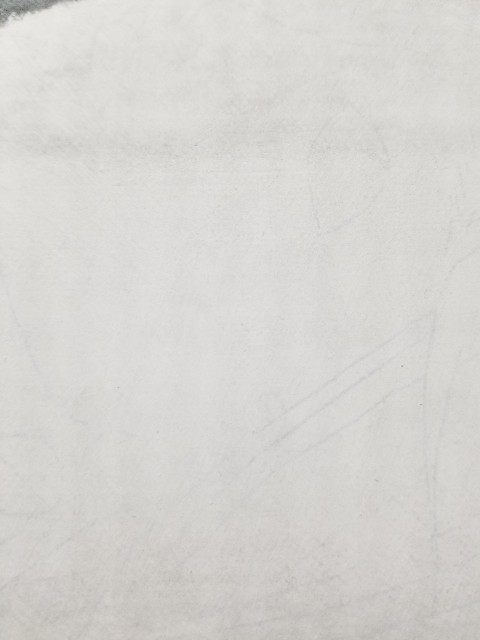
磨いた後
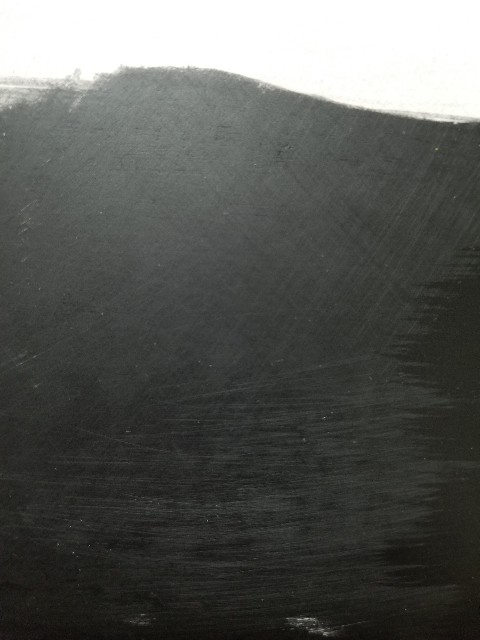
黒いところだと分かりやすいですが、このように細かい傷をどんどんつけて磨きます。
紙ヤスリで磨きます。
数字が小さい方がヤスリの目は荒く、大きな数字になっていくと細かくなります。
最初荒いものから~最後は超大きな数字の細かい目をしたやすりを使います。
この作業は木工なんかで家具作るときも仕上げの行程としてありますが、最初はざらざらだった面が手をかけ時間をかけ丁寧にやすっていくとさらっさらっの面になります。
結果的にいとおしくてしょうがなくなります。
絵でも同じ気分でさらさらの面ができるとほおずりしたくなります。
絵の組み立ての中で凹凸面と平滑な面を組み込むと個人的に視覚的に気持ちいいなあと感じるので地味だけど大事な作業。
手を抜かずにやっております。
さて、今日も池上英洋さん著「西洋美術史入門<実践編>」を読んでいます。
退廃芸術って聞いたことありますか?
前回ナポレオンが占領下の国の美術品を多数略奪し、今も返還されずルーヴル美術館にある作品が存在していることを書きました。
ナチス・ヒトラーも同じように占領下の国の作品を「退廃的」として没収します。
ヒトラーの著書「わが闘争」の中で、キュビズムや未来派、表現主義、ダダイズムやシュルレアリスムなどの同年代の美術は退廃芸術として批判されていました。
これは、1892年にユダヤ人医師マックス・ノルダウの著書「退廃論」で示した理論が基となっています。
ヒトラーは没収した作品を、避難すべき芸術を知らしめる教育目的のため1937年にミュンヘンの退廃美術展で展示ました。
退廃美術展は展示が替えをしつつ全土を巡回し1941年まで続きます。
そして1939年からはスイスのオークションなどでその作品を売り出し始めます。ここで稼いだ外貨はナチスの資金源になったと言われます。
ヒトラーは若い頃画家を目指していたほど美術に関心を持っていました。
しかしベルリン国立美術館のカラヴァッジョの作品を見て「さすがミケランジェロ!」とかんたんしたそうです。カラヴァッジョのフルネームはミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ。キャプションの名前を見て勘違いしたそうです。なんと。
今日はここまで。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
明石 恵 Aya Akashi website - 明石 恵 Aya Akashi website